臨床心理学ことはじめ③ 〜実践活動〜
- 2017.10.06
- 臨床心理学
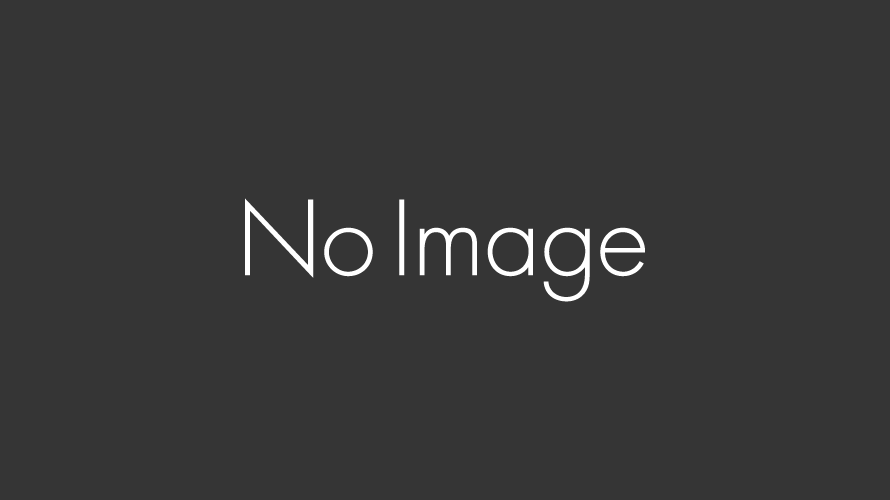
さて、前回臨床心理学には「実践活動」「研究活動」「社会活動」の3つの活動がある、ということを説明しました。今回の稿では、このうちの「実践活動」について、具体的に何を行うのか説明していきます。
実践活動の2本柱「アセスメント」と「介入」
何らかの心理的な問題を抱えた非援助者=クライアントが、援助者=セラピストの元を訪れることから実践活動は始まります。そして、相談者が抱える問題が何かということを色々な視点からまず把握したあと、臨床心理学における「知識」やその他の心理学的知識を用いることで、その問題がなぜ生じているかを考えます。
そうして考えた結果、この問題はこうして発生している、だからこうすれば軽減できるはずだ、といった仮説を立て(ここまでの流れを「アセスメント」と呼びます)、これをもとに問題を変えようと現実に実際に働きかける、つまり介入していきます。アセスメントによって問題を理解し仮説を立ててから、それを元にして介入していくのです。この「アセスメント」と「介入」の二つの段階は、実践活動における二本の柱とでもいえるものです。(図1)
とは言っても、実際の実践活動ではアセスメント→介入の一回の流れで問題が解決する、ということはまずありません。このように介入がうまくいかなかった場合、セラピストは再び問題についての仮説を修正し、それに基づいて再び介入する必要があります。
一回目の稿でも説明したように、一つの心理的問題にはそれだけでも多くの要因が考えられます。不登校が問題だったとして、クライアントの考え方をまず変えようとすることもできるし、クライアントの取りがちな問題行動そのものに着目して、それを直接的に変えていこうとすることも出来るでしょう。そして、これら多くの要因について考えるときにあくまで参考として、臨床心理学の「知識」やその他の心理学的な知識が補助的に用いられます。それぞれの要因を想定して問題を説明しようとする理論が、いままで提案されてきています。ですから、ある一つの要因に介入してもやはり問題が解決しなかった場合には、別の考えられる要因について再度考えることで仮説を作りなおし、再び介入していくことになるのです。
こうしてみれば、臨床心理学における実践活動とは、「アセスメントと介入を交互に繰り返すことで、相談者の問題を改善しようと試みる活動である」と言うことが出来るでしょう。(図2)
どのアセスメント・介入方法を選ぶか?
さて、アセスメントによって問題を理解・仮説を立て、それに基づいて介入するのが実践行為ですが、アセスメントと一口に言ってもたくさんの方法がありますし、介入方法もさまざまです。
問題がどのような状況のとき、どのようにアセスメントし介入していけば効果的なのか?実を言うと、この質問に対する明確な答えはまだない、というのが現状です。というのも、多くのセラピストは自分が主に訓練を受けた、ある特定の心理療法の理論をもとにアセスメントと介入を行っているからです。
臨床心理学における理論は、心理的な問題がなぜ生じるかをそれぞれ独自の要因を用いて説明しています。これら独自の要因についての情報を収集するために、各理論では独自のアセスメント手法が考案されています。例えば認知療法の理論では、うつ症状をさらに悪化させる特定の考え方(要因)があるとしたうえで、そのように考える傾向がどの程度クライエントにあるかを測定するための質問紙が考案されています。更に、この特定の考え方を変えるための具体的な技法も、認知療法の理論を土台として作られてきました。
ほとんどのセラピストは研修段階で、どの心理療法アプローチを訓練していくかを迫られます。認知療法的アプローチを主に訓練したセラピストはやはり、認知療法の理論とそれに基づいたアセスメント技法・介入技法を用いて問題を改善しようとするでしょう。しかし、多くのセラピストは自分の主とするアプローチに固執せず、他の心理療法の理論や技法を積極的に組み込む努力をしています。このように異なる心理療法を組み合わせることで、援助の効果を高めようとするような統合的アプローチは現在、一般的になりつつあります。
また、どのような心理的問題にどのような心理療法が効果的かをより科学的に研究し、以降の実践に役立てようとする「エビデンスベイスド」という考え方も主流になってきています。心理的問題を症状によって分類し、それぞれに有効な心理療法を調べてデータ化しておくことで、ある症状に対してどの心理療法アプローチを用いるとよいのか、アセスメント時に参考にすることが出来るでしょう。
アセスメントや介入の方法はよって立つアプローチによって様々ですが、いずれにせよ、ひとつの見方にとらわれないで様々な理論から問題を捉えようとする柔軟性が、セラピストには常に求められると言えるでしょう。