子どものしつけは優しくするべきかを心理学的に考えてみる【認知的不協和】
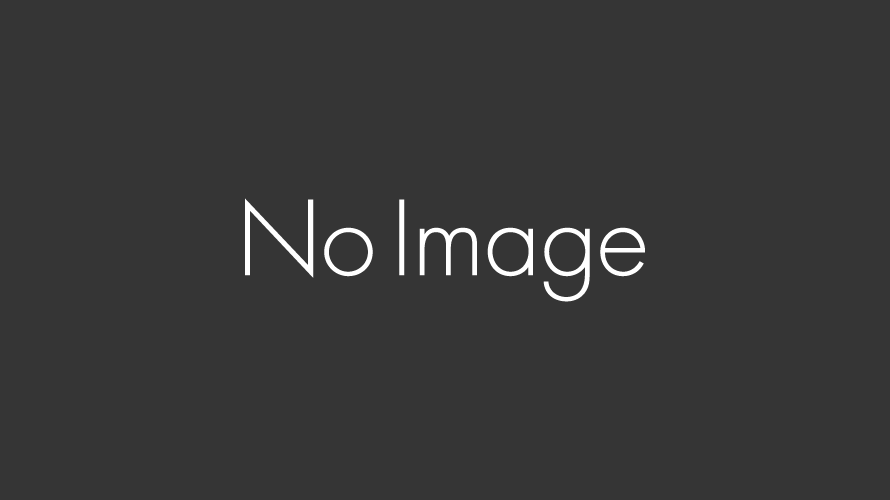
子どものしつけって、優しく「こういうことはやっちゃだめだよ。」という風に教えるのか、厳しく、時には怒鳴るようにしつけるのかという問題がありますよね。今回は、少し古典的な実験に、子どものしつけに役立ちそうなものがあったので、この問題を心理学的に分析してみたいと思います。
諭すが良いか、叱るが良いか
結論として、これは優しく諭すことが効果的であるといえるでしょう。もちろん、それぞれの家庭の方針は存在するし、時には叱ることも大切な状況もありますが、あくまで心理学的な一つの見方というていで見てください。さて、それでは具体的になぜ心理学的に見ると、諭すことが子どものしつけに良いのか、ある実験をとりあげて説明しましょう。
その実験というのが、「禁じられた玩具」の実験です。これは、認知的不協和という社会心理学における概念を調べた実験の一つで、子どもに対して玩具を使ってはいけないことを伝える方法によってどのような子どもの態度変化が生じたかを調べました。また、認知的不協和とは自分の行為によって生じたモヤモヤとした感情のことで、かつそれを正当化する方法を示す体系のことを言います。次の章で認知的不協和の具体的な例を見ていきましょう。
認知的不協和とは
再掲にはなりますが、
認知的不協和とは自分の行為によって生じたモヤモヤとした感情のことで、かつそれを正当化する方法を示す体系のこと。
です。このモヤモヤした感情とは、例えばこんな感じです。
Aさんはヘビースモーカーです。しかしながら、Aさんの妻は、子どもに影響するからやめてとAさんのタバコを毛嫌いします。この時、Aさんはタバコを吸うたびにこのことを思い出し、何か嫌な感情が生まれます。
この嫌な感情こそが認知的不協和なのです。また、これに対する正当化のことも認知的不協和の概念の中に入ります。例えば、
・タバコを吸うことを事象xとする。
・妻からの圧力を事象yとする。
このことを念頭に置くと、Aさんはどのようにこの不協和を解消しようとするかというと、①事象yを変更する,②新たな事象zを追加する。の2パターンです。①に関してはわかりやすいと思います。妻を説得しようとするわけです。これによって妻はAさんへ圧力をかけようとはしません。これによって不協和が解消されるわけです。また、②に関しては、たばこを吸うことがいかにAさんにとって利益があるかという理由を探してくるということですね。たとえば事象z[たばこを吸わないと仕事のモチベーションが上がらない]という理由を追加するわけです。これによって、Aさんは自分はたばこを吸う必要があるのだからという正当化ができて不協和が解消されます。また人は不協和が生じたとき、たいてい事象yは変わらないので、事象zを加えることによって正当化しようとします。このことを「禁じられた玩具」実験から確認してみましょう。
禁じられた玩具実験
この実験の概要は以下のとおりです。
子どもが玩具の沢山ある部屋に入れられました。実験者は子どもに対して、ある玩具にだけは絶対に触らないように指示しました。この時、ある子どもには優しく、その玩具にだけは触れないでほしいことを話しました。またある子どもには物凄い剣幕で怒鳴るように玩具に触らないことを話しました。そして、その実験者がいる部屋で遊んだ後に、その実験者がいなくなった部屋で、優しく話された子どもたちはそのおもちゃには触れずに他のおもちゃで遊びました。しかしながら、怒鳴られた子どもたちは禁じられた玩具も使って遊んでいました。
この結果はどういうメカニズムかというと、
事象x:おもちゃで遊ばない
事象y:実験者にある玩具を禁じられる
という事象がある中で、怒鳴られた子どもたちは「怖い実験者がいたからそこでは遊ばなかったんだ」という自分が遊ばなかったことに対する正当化が可能です。これによって、事象yが無くなった時点で、認知的不協和は解消されて実験者がいない部屋ではそのおもちゃを使ったわけです。一方で、優しく言われた子どもたちには「特に怖くないのにそのおもちゃで遊ばなかった」という認知的不協和が残るわけです。そう、怒鳴られた子どもは「怖い実験者がいた」という自分がそのおもちゃで遊ばなかった正当化ができるのに対して、優しく言われた子どもはそのような正当化の手段がないわけです。事象yが変わらないということでもあります。こんな時、人はどのようにして不協和を解消するのでしょうか。
そう、新しい事象zを追加するのです。ここでは、子どもたちはどのような事象zを追加したというと、「自分はこの玩具を使いたくなかったから使わなかったんだ」や「自分はいうことを聞く子どもだから使わないんだ」といったところです。
諭すことが良い理由
これらのことから、子どもに怒鳴ることは「親が怖いからやらない」という、本当にそれがやってはいけない理由が分からない状態になります。そこまではいかずとも、親がいないときはやってやろうという考えが浮かんでくる可能性が大きいと言えるでしょう。逆に、優しく諭してあげることで、子どもは自分がそれをやらなかった理由を探し出します。もちろん、先ほどの実験の結論から言うと、「親が言ったからやらない」という理由を探しだすこともありますが、きちんと正しい理由を教えてあげることで、それを理解することでしょう。心理学的に言うと、正しい理由によって認知的不協和を正当化するでしょう。